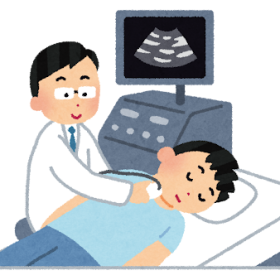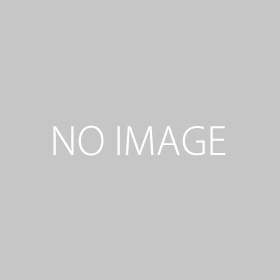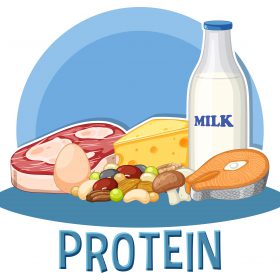みなさま、こんにちは
嚥下は咽頭だけが関係しているわけではないことはもちろんご存じだと思いますが、なかなか歯にまで目が行かないこともあるのではないでしょうか?
嚥下内規鏡を施行していると、その画像は咽頭にスポットを当てているので、口腔内の様子を観察を怠ってしまうこともあるので、内視鏡の折には口腔内でどんなことが行われているかを想像しながら、画像を見ることはとても大切だと思います。
そこで、今回は歯と嚥下について書きたいと思います。
歯と嚥下(飲み込み)には密接な関連性があります。嚥下は食物や飲み物を口から喉を通して食道に送り込む過程ですが、この過程には口腔内の構造、特に歯が重要な役割を果たしています。
以下のような関連性が考えられます:
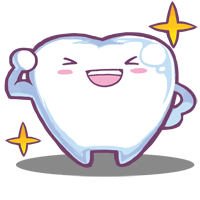
1. 食物の咀嚼
歯は食物を咀嚼する役割を担っています。咀嚼によって食物が細かく砕かれ、唾液と混ざりやすくなり、飲み込みやすい形状(嚥下しやすい塊)になります。歯が欠損していると、食物が十分に咀嚼されず、大きな塊のまま嚥下することになり、これが嚥下障害を引き起こす原因となることがあります。
2. 口腔内の感覚
歯が舌と接触することで、舌が食物の塊を適切に感知し、正しい嚥下動作を促進します。歯の位置や状態が悪いと、舌の感覚や運動が影響を受け、嚥下がスムーズに行われないことがあります。
3. 嚥下反射の誘発
咀嚼が終わると、食物の塊(ボーラス)が舌の後ろに運ばれ、嚥下反射が引き起こされます。歯が健全であれば、食物が適切に形成され、嚥下反射が正常に働きます。しかし、歯が欠損したり、噛み合わせが悪いと、ボーラスの形成に時間がかかり、嚥下反射が遅れることがあります。
4. 口腔と咽頭の協調
嚥下には口腔から咽頭にかけての筋肉や神経の協調が必要です。歯が欠損していると、嚥下に必要な口腔内の協調動作が不十分になる可能性があり、食物が喉にうまく移動せず、誤嚥(食物や飲み物が気管に入ってしまうこと)や窒息のリスクが高まることがあります。
5. 歯の健康と全身の健康
歯の健康が悪化すると、口腔内の清潔が保たれにくくなり、細菌の繁殖が進んで感染症を引き起こす可能性があります。感染症が原因で嚥下に関わる筋肉や神経に影響を与えると、嚥下障害が起こることもあります
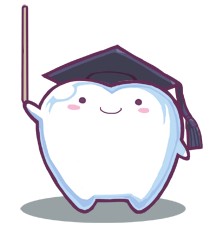
歯と嚥下の関係をさらに詳細に理解するためには、口腔内の構造と嚥下のプロセスを細かく見ていく必要があります。嚥下は非常に複雑で精密な過程であり、その中で歯は重要な役割を果たします。以下の点を詳しく掘り下げて説明します。
1. 食物の咀嚼と歯の役割
嚥下の過程の最初は「咀嚼」です。咀嚼は、食物を口の中で歯を使って細かく砕くことで、食物を嚥下しやすい状態に変える重要なステップです。
-
歯の機能:歯は食物を細かくするために不可欠です。特に臼歯(奥歯)は、大きくて硬い食物を噛み砕く役割を担っています。前歯は食物を切り、臼歯でそれを細かくします。
-
咀嚼の効率:歯が欠損している場合、食物を十分に噛むことができません。その結果、食物の塊が大きすぎて、喉にスムーズに送ることが難しくなり、誤嚥や窒息のリスクが高くなります。また、噛み合わせが悪いと、食物が不均等に砕け、嚥下時にうまく咽頭へ送ることができません。
2. 唾液の分泌と嚥下の準備
唾液は、食物を湿らせて飲み込みやすい塊にするために必要不可欠です。歯が健康であれば、正常な咀嚼とともに唾液が適切に分泌されます。唾液には以下の役割があります:
-
食物の潤滑:唾液が食物と混ざることで、食物が柔らかくなり、飲み込みやすくなります。唾液の分泌が不十分だと、食物が喉に引っかかりやすくなり、嚥下障害を引き起こす可能性が高くなります。
-
歯の保護:唾液は歯を保護する役割も担っています。唾液には歯を酸から守るカルシウムやリンが含まれており、歯の健康を保つために重要です。歯が健康であれば、嚥下時に歯が食物をしっかりと噛み、飲み込みやすくするためのサポートをすることができます。
3. 舌と歯の協調
舌は嚥下の際に非常に重要な役割を果たします。歯は、舌が食物を適切に感知し、口腔内で食物をまとめて、咽頭へ送り込むための支えとなります。舌と歯の協調は以下のように進行します:
-
食物の移動:舌は食物の塊(ボーラス)を前歯の周囲で感じ取り、後ろに押し込んでいきます。この過程で、舌と歯が協調して働く必要があります。歯が欠けていると、舌は食物の塊を効率よく操作することができず、ボーラスがうまく形成されないことがあります。
-
嚥下反射の誘発:ボーラスが舌の後ろに到達すると、喉の筋肉が収縮して食物を食道に送り込む反射が始まります。歯が健康であれば、舌はスムーズに食物を後ろに運び、適切に嚥下反射が引き起こされます。
4. 嚥下反射とその制御
嚥下反射は自動的に起こるものですが、その過程には神経系と筋肉の協調が必要です。嚥下には以下の段階が含まれます:
-
口腔期:食物が口の中に入ると、舌が食物を後ろに押し、喉の奥へ運びます。この段階では歯が食物の形成に重要な役割を果たします。歯が正常であれば、舌が食物をうまく集めて食道に送ることができ、スムーズな嚥下が促進されます。
-
咽頭期:食物が喉に到達したとき、咽頭の筋肉が収縮して食物を食道に送ります。舌と歯の協調が不十分だと、食物が適切に喉に移動せず、誤嚥を引き起こすことがあります。
-
食道期:食物が食道に移動し、最終的に胃に達します。この段階では、舌や歯の影響は少なくなりますが、初期の嚥下段階が適切に行われることが重要です。
5. 歯の欠損と嚥下障害
歯が欠けている、または歯並びが悪いと、咀嚼や嚥下に大きな影響を及ぼします。特に歯が欠損していると、食物を十分に噛むことができず、以下のような問題が生じる可能性があります:
-
誤嚥のリスク:咀嚼が不十分なため、食物が喉にうまく送られず、気管に誤って入る可能性が高まります。これにより、誤嚥性肺炎などの健康問題が発生することがあります。
-
噛み合わせの問題:不正咬合(噛み合わせが悪いこと)があると、食物を噛む効率が低下し、ボーラスの形成が不十分になることがあります。これにより、嚥下がスムーズに行えなくなることがあります。
6. 口腔と全身健康との関連
歯の健康は全身の健康に大きな影響を与えます。特に、嚥下に関連する筋肉や神経が損なわれると、嚥下機能が低下し、栄養摂取に問題が生じます。また、歯の健康が悪化すると口腔内に細菌が繁殖し、嚥下に関わる筋肉や神経に炎症を引き起こすこともあります。
結論
歯と嚥下は密接に関連しており、歯の健康が嚥下機能に直接的な影響を与えます。歯が健康であることは、食物をしっかりと噛み、嚥下をスムーズに行うための基盤となります。歯科的なケアを行うことは、嚥下障害の予防や改善にもつながります。嚥下に問題がある場合は、歯科と医療の協力が重要です。




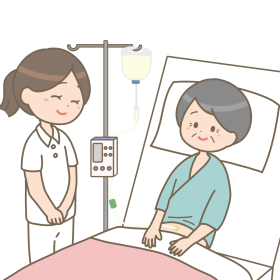

-1-280x280.png)